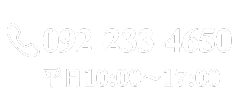
税務調査
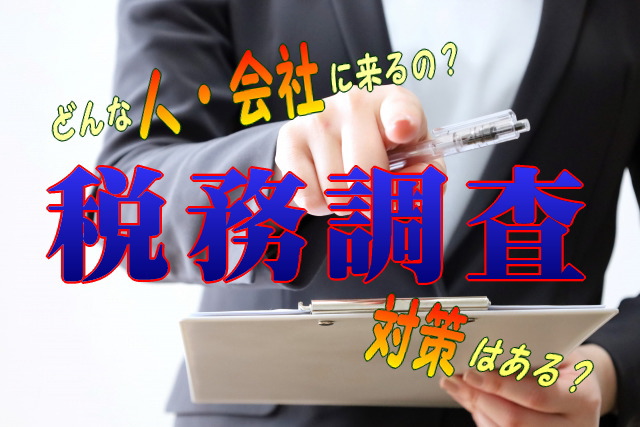

税務調査は、法人にも個人事業主にも行われる可能性があり、いつ自分の会社に訪れても不思議ではありません。
税務調査の連絡が入ったと聞けば、何らかの指摘を受けて追徴課税を納付しなければならないと考える方もいるでしょう。
税務調査は税金を正しく申告・納付していれば問題ありませんが、調査の流れや事前準備について知っておくことが大切です。
目次
税務調査とは
税務調査は、申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を求めるものです。
国税庁ホームぺージより
税務調査とは、納税者が正しく税務申告を行っているかを税務署が調査するものです。
毎年、一定の割合の納税者が税務調査を受けています。
税務調査時に「申告漏れ」の指摘を受けて修正申告した場合、「延滞税」「過少申告加算税」というペナルティが課せられます。
一般的に個人事業主で税務調査に入られることは少ないですが、法人の税務調査は定期的に実施されることが多いです。一般的に5~10年に一度のペースと言われています。
そのため法人として事業を運営されている場合は、税務調査対策も考えておきましょう。
税務調査の種類
税務調査には、大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。
1. 任意調査

申告が正しく行われているかを税務署職員が調査するもので、税務調査の大半がこのパターンです。
5~10年に一度程度の頻度で行われ、2日ほどかけて帳簿などを調べられます。調査の連絡は事前に行われます。
国税庁の職員には、必要な時に納税義務者に対して質問・検査等ができる質問検査権が与えられています。“任意”調査とはいえ、調査を拒否したり正当な理由なく帳簿を見せなかったりすると、法律で定められた罰則がありますので、実質的には強制と考えてよいでしょう。
税務署側は事前に事業者の申告内容を確認していると想定されます。そのため、確認したい資料を指定してくることもあります。また、税務代理を委任された税理士等に立ち会ってもらうことが可能です。
税務署職員が調査対象企業を訪問して行う任意調査は「実地調査」と呼ばれます。なお税務署内で申告内容を確認し、実地調査をすべきか判断する「準備調査」というものもあります。
税務調査に来る前に、事前にある程度情報を収集されている場合が多いので、嘘や不正は基本的に見抜かれると考えておきましょう。
2. 強制調査

事前の連絡なしに突然調査員が訪問するもので、国税局査察部が実施する調査です。いわゆる「マルサ(※)」といわれる調査員が裁判所の令状を持って事前連絡なく強制的に行われるもので、調査対象となった場合は拒否できません。巨額の脱税などの悪質性が高く、事前に通知すると証拠隠滅される恐れがある場合には強制調査が行われます。
(※)国税局の国税査察部の俗称。査(サ)の字を丸で囲って「マルサ」とされている。
税務調査の時期

税務調査が行われる時期は特に決まっているわけではありません。
個人事業者であれば、所得税の確定申告期間中(2月16日〜3月15日)やその前後は調査を受ける可能性は低くなります。一般的な傾向として、3月の確定申告時期明けの4月~5月ごろと、国税局や税務署の人事異動が終わる7月~11月ごろに行われることが多いといわれます。
いつ税務調査が行われても適切な対応がとれるように準備しておくことが大事です。
税務調査が入りやすい個人・法人の特徴

税務調査は一般的に5~10年に1回程度といわれますが、5年ごとに調査される事業者もあれば、ほとんど調査されていない事業者もあります。実は調査されやすい法人の特徴があるのです。
税務調査が入りやすいといわれる個人・法人の特徴
個人
- 申告書に不備がある
- 無申告
- 税理士を使わずに自分で確定申告した場合
- 相続額が大きい(2億円以上)
- 調査されやすい業種:飲食店や風俗店、IT関連業、建設業
FXやデイトレード、仮想通貨など、投資で生計を立てている人も注意が必要です。 - 海外資産が多い
- 相続財産に現金・預貯金や入出金回数が多い
- 生前に不動産所得や株式譲渡などがあったのに申告額が少ない
法人
- 売上の変動が大きい
- 同規模の同業他社と比較して、利益率が大幅に低い
- 売上の増加に対し、利益が少ない
- 計上額が前年度と大幅に違う
税務調査(任意調査)の流れ

税務調査は、以下の流れで進行しますが、顧問税理士がいる場合といない場合では流れが異なります。
1. 税務署からの事前通知

まず、税務署から税務調査を行う旨の事前連絡があります。
事前連絡の内容は、「開始日」・「開始場所」・「調査の目的」・「調査対象税目(法人税、消費税、など)」・「調査対象期間(直近3期分、など)」などです。
税理士が申告書に税務代理権限証書を添付して申告していた場合は、税理士に連絡が入ります。
2. 調査実施日の日程調整
事前通知後、税務署と調査実施日を決定します。日時の都合が悪いとわかっている場合は、調整してもらうことが可能です。
税理士に立ち会ってもらう場合、税理士とも日程調整しておくことが大切です。
顧問税理士がおらず、対応が不安な場合は、税理士を探すことをおすすめします。質問も税理士が答えてくれる場面も多くありますので、税理士に任せると安心です。

3. 必要書類を揃える
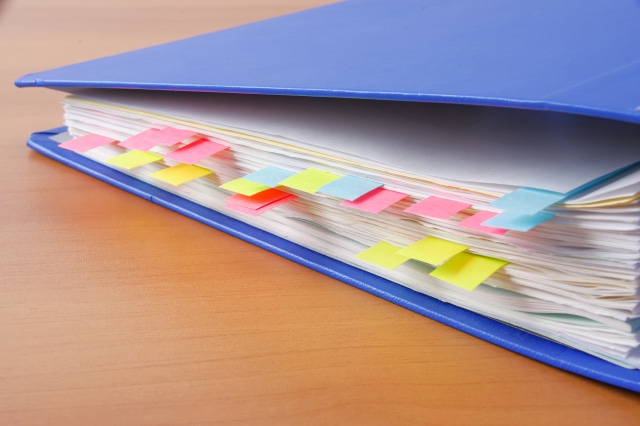
税務調査前に必要書類を揃えます。
顧問税理士がいる場合は、調査前に税理士と打ち合わせをして、揃えるべき資料を確認したり、申告内容を再度確認しておきます。調査当日に聞かれそうなことなども想定して準備しておきましょう。
4. 調査当日
税務調査当日は、税務調査官が会社や事務所などを訪れます。多くの場合、税務調査は2~3日間にわたって行われます。
※新型コロナウイルスの影響により、税務調査官が会社や事務所を訪れる日数を1日とし、書類を持ち帰って調査が行われるケースも増えています。
調査前に、申告内容の確認で税務調査を行うこと、実施期間や担当者の紹介などの説明を受けて開始されます。
1日の調査時間は午前中から夕方頃までで、お昼には休憩時間も設けられるのが一般的です。調査期間中は税務署からの質問に答える必要があるため、代表や経理責任者は同席する必要があります。

5. 税務署の指摘に対して回答する

税務職員の実地調査が終わっても、税務調査はまだ続きます。
調査結果を踏まえて税務署から指摘や質問があり、それに対する資料の準備・回答などのやりとりを行います。また、追加で資料の提出を求められることもあります。
顧問税理士がいない場合は事業者自身が、顧問税理士がいる場合は税理士が交渉を行います。交渉が終わり、調査結果が決定するまでの期間は1か月以上かかるのが一般的です。
6. 調査結果
税務調査の結果には、「申告是認」「修正申告」「更正」という3つがあります。
「申告是認」とは申告内容に何も問題がないことです。
「修正申告」は税務署の指摘を認めて自分で申告をすることです。修正申告などを行った場合、「不服の申し立て」はできなくなります。
「更正」とは税務署の指摘に対して、納税者がその指摘を納得せず修正申告を出さない場合に、税務署側が各税法の規定を根拠に行なう課税処分のことです。税務調査において修正申告などを求めるための立証責任は税務署にありますが、「更正の請求」を実施する場合には、事実認定の責任は納税者側が負うことになります。

税務調査での注意点は?
故意に脱税行為をしていなくても、緊張したり、戸惑ったりすることも多い思います。
スムーズに調査を進めるために、以下の点に注意しましょう。
1. 帳簿類は取り出しやすい状態にする

すべての書類に目を通すわけではありませんが、準備してほしいと要望されたものはすぐ取り出せるように準備てしておきます。
税務調査で準備しておくべきもの
税務調査において準備すべき書類やデータは、調査の対象となる期間や内容によって異なりますが、以下に一般的に準備すべきものを挙げます。
- 決算書類
損益計算書、貸借対照表、補助帳簿、試算表などの決算書類を用意してください。 - 税務申告書類
所得税、法人税、消費税などの税務申告書類およびその添付書類を揃えておきましょう。 - 帳簿類
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、給与台帳、棚卸帳など、事業に関連するすべての帳簿を準備してください。 - 領収書・請求書・契約書
税務調査に関連する取引や経費の証明となる領収書、請求書、契約書などの書類を用意しておくと良いでしょう。 - 銀行取引明細
銀行口座の取引明細書や通帳、クレジットカードの利用明細書など、金融機関との取引に関する記録を準備しておきましょう。 - 事業に関連する許可証や免許
事業に必要な許可証や免許を持っている場合、それらのコピーを用意しておくと良いでしょう。 - 給与支払証明書
従業員に支払った給与に関する証明書や源泉徴収票を揃えておきましょう。
税務調査が始まる前に、これらの書類やデータを整理・確認しておくことで、調査がスムーズに進むことが期待できます。また、税理士に依頼している場合は、税務調査に関するアドバイスや指示を受けて、必要な書類を準備しましょう。
2. 世間話に気を付ける!

調査官は聞き取り調査のプロです。時々挟まれる世間話のように聞こえる会話から、知りたい情報を引き出すここともあります。
警戒するあまり何も答えなかったり、質問に対し上手く説明できなかったり、つじつまが合わないことを言ったりすると、虚偽の発言・申告をしていると疑われる可能性があります。注意深く冷静に対応しましょう。
また、感情的に対応して調査官の心証を悪くするのも得策ではありません。感情的になることなく、かつ、こちらが正しいことは毅然として主張することが大切です。
税務調査の負担を軽くするには
税務調査は、正しく処理されているなら特に指摘事項もなく、かえって事業者として好印象を与える機会にもなります。税務調査を問題なく進めるためには、日々の会計を正しく処理し、適正な申告を行うことが重要です。
書類の整理・保管

調査当日までに用意すべき資料は、取り出しやすく整理しておきましょう。
調査で確認される資料は、基本的には一定期間の保存が義務付けられている帳簿や書類です。帳簿書類の保存期間は7年とされています(欠損金を生じた年度については、青色欠損金の繰越控除を受けるために10年保存が必要とされています)。
また、帳簿を電子化すれば紙として大量に保管する必要がなくなるため、省スペース・確認作業の効率化に繋げられます。さらに経理業務の負担が軽減されるとともに、税務調査にも有効です。
顧問税理士を契約しておく

日頃から税理士などと相談しながら正しい納税を行うことが、結果的に調査での負担を軽くすることにつながります。
顧問を依頼している税理士がいる場合、税務調査の連絡や質問も、税理士のもとへ問い合わせてもらうことができます。税務署の疑問に対して税理士が明確に対応できれば、実地調査自体が回避できる可能性もあるのです。
税務調査は1度だけでなく、会社を続けていればその後何度も調査対象となる可能性があります。税理士へ依頼していれば、申告で大きなミスをしたり、勘違いで科目の入力ミスをしたりして指摘を受けるリスクも減らせます。そのうえ、節税対策についてもアドバイスがもらえるため、結果的に支出を大きく抑えることができます。
3. 税理士に立ち会いを依頼する

税務調査での対応の手間を減らすには、税理士に立ち会いを依頼することをおすすめします。税務調査官の指摘が間違っている場合、税理士なら適切に対応することが可能でしょう。
税務調査を税理士に依頼するメリット
税務調査においては、税理士の支援を受けることが望ましいです。税理士は、納税者の代理人として税務調査に対応することができ、納税者の利益を最大化するための戦略を立てることができます。
税理士の支援を受けることで、税務調査による負担を軽減し、納税者の利益を最大化することができます。
税務調査を税理士に依頼するメリットはいくつかあります。以下に主なメリットを挙げます。
- 専門的知識の活用
税理士は税法や会計に関する専門的知識を持っているため、税務調査において適切な対応ができます。税務調査の過程で複雑な税法の解釈や計算が必要になる場合、税理士の専門的知識が大変役立ちます。 - 税務調査の進行管理
税務調査は、書類の提出や説明が求められるため、時間と労力がかかることがあります。税理士に依頼することで、税務調査の進行管理を円滑に行い、事業者が本業に専念できるようサポートします。 - 交渉力の活用
税務調査では、税務署との交渉が発生することがあります。税理士は税務署との交渉経験が豊富で、適切な交渉を行うことができます。その結果、追加税金の軽減や納税猶予の交渉が円滑に行われることが期待できます。 - 税務調査後のフォロー
税務調査が終了した後も、税理士は税務調査に関するアドバイスや改善策を提案してくれます。これにより、今後の税務リスクを軽減することができます。 - 緊張感の緩和
税務調査は、事業者にとってストレスがかかることがあります。税理士が間に入ることで、事業者と税務署との緊張感を緩和し、円滑なコミュニケーションが図られます。
これらのメリットから、税務調査を税理士に依頼することは、事業者にとって有益です。ただし、税理士に依頼する場合、報酬が発生することを考慮し、適切な税理士を選ぶことが重要です。
申告漏れがあった場合の罰金
税務調査の結果、申告漏れが見つかった場合は修正申告が必要です。
そして3種類に大別されるペナルティが課されます。
- 延滞税:納税を期限内にしなかった場合に課せられる延滞利息の意味を持つ税金です。
- 加算税:税金を正しく申告しなかったことに対する懲罰としての税金です。
- 2-1 無申告加算税|本来は申告が必要であったのに、期限内に申告しなかった場合に課せられる税金です。
わざと申告しなかったのではなく、必要ないと思っていたり、うっかりしていた人は、これに当たります。
正しい納税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分には20%が加算されます。 - 2-2 過少申告加算税|申告はしたが、相続税額が本来よりも少なくなってしまっていた場合に課せられます。
わざと申告しなかったのではなく、気づかず申告漏れがあったり、財産の評価や計算を間違えていたりした人に当てはまります。
納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)に相当する過少申告加算税が課せられます。 - 2-3 重加算税|過失ではなく、故意に財産を隠したり少なく偽装した、または不当に少なく申告した場合に課せられます。
税率は、無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%と思いものになります。
- 2-1 無申告加算税|本来は申告が必要であったのに、期限内に申告しなかった場合に課せられる税金です。
- 刑事罰:悪質な脱税と判断された場合は犯罪として裁かれます。
故意に財産を隠したり少なく偽装するなど、特に悪質な脱税事件と判断されると、逮捕・起訴され、裁判によって刑事罰が課せられることもあります。
相続税法第68条により、偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金とが課せられる重大な犯罪です。
まとめ

税務調査は、基本的には申告内容や納税額が適正であるかを調査する目的で行われるため、適正に申告できていれば問題ないものです。
とはいえ、自分だけでは明確な説明や対応ができるか不安があることでしょう。
不安な場合は税理士のサポートを受けて、日ごろの適正な会計と税務調査時の交渉を適切に行い、事業に注力しましょう。
執筆者

野村税理士事務所代表 野村真一
税理士業界20年、野村税理士事務所代表でfreee認定アドバイザー。日本税理士会連合会、九州北部税理士会所属。認定経営革新等支援機関の認定事業者として事業再構築補助金の申請支援を行う。
